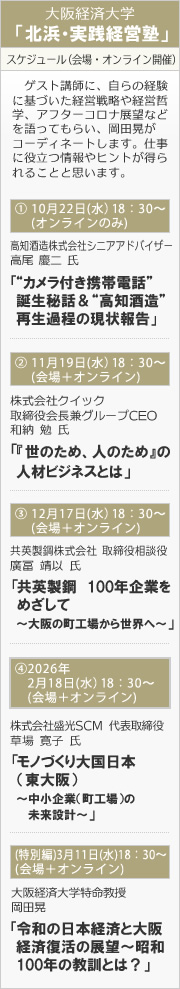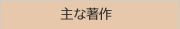Vol. 36 「未曽有の危機」に立ち向かった日本人(『歴史街道』2020年8月号特集より)
大火、飢饉、外圧と闘った幕閣
(2020年09月19日)
250年以上もの泰平の世が続いた江戸時代。しかし、そんな時代にあっても、いくつもの未曾有の危機は起こっていた。明暦の大火、天明の大飢饉、ペリー来航……。時の為政者はその危機にどう対処したのか。
保科正之――明暦の大火から江戸を復興
「火事と喧嘩は江戸の華」と言われたものだが、江戸時代最大の大火は明暦3年(1657)の「明暦の大火」、いわゆる振袖火事だ。
1月18日(旧暦、月日は以下同)、本郷から出火し、瞬く間に江戸中に広がった火事は二昼夜におよび、大名屋敷と旗本屋敷の大部分と町屋四百町余り、当時の江戸市街地の約60%が焼失した。死者は10万人以上、当時の江戸の人口の15%に達したという。
江戸城も天守閣をはじめ本丸、二の丸、三の丸が焼け落ち、無事だったのは西の丸だけだった。四代将軍・徳川家綱は本丸から西の丸に避難し、さらに西の丸にも火の粉が飛んできたため、一時は城外に避難することが検討されたという。
この時の対応に陣頭指揮を執ったのが、将軍の後見役だった会津藩主・保科正之である。
正之は二代将軍・秀忠の子として生まれたが、いわば隠し子のような存在で、信州高遠2万5000石の藩主だった保科家に養子に出され、長じて保科家を継いでいた。
父・秀忠の死後、異母兄である三代将軍・家光に見いだされて信頼されるようになり、会津23万石の大名に出世して家光を補佐したが、家光が死去し家綱が四代将軍に就任すると、大老格の大政参与に就任、幕府の事実上の最高実力者となっていた。
明暦の大火の際、正之がまず取り組んだのは被災者救援だった。鎮火直後に、いち早く江戸の6カ所で粥の給食を行った。今で言う炊き出しだ。
当初は9日間の予定だったが延長され、2月12日まで続けた。幕府の米蔵に貯蔵されていて焼けた米も、食料として提供した。
家を焼け出された町民には救助金を支給した。焼失した町屋の間口一間当たり金三両一分などとして、支給総額は16万両にのぼった。現在の貨幣価値で160億円程度。
幕閣からは「ご金蔵がカラになる」と反対する声が上がったが、正之は「幕府の貯蓄は、こういう時に使って民衆を安堵させるためのもの。いま使わなければ意味がない」と一喝したという。
物価の安定にも重点的に取り組んだ。米価の上限を定めるとともに幕府備蓄の米を放出、安売りも行った。
正之はまた、江戸にいる諸大名に帰国命令を出し、国許にいる大名には、参勤交代で江戸に来るなと通知した。江戸に滞在する各藩の家臣の膨大な人数を減らすことで、米の需要を緩和し値上がりを抑えようとしたのだ。
参勤交代制度は幕府の大名統制の中核をなすものだが、正之の考えは柔軟だった。非常時にあって何が最優先かを見きわめていたのだった。
その考えは江戸城再建でも発揮された。幕府は本丸御殿や二の丸、三の丸を再建していったが、天守閣の再建に正之は反対したのだ。「今のような時に天守閣を建設するのは、庶民の迷惑になる」と言ったという。
天守閣より江戸の町の復興を優先すべきとする考えに、優れたリーダーシップを見ることができる。 ちなみに、江戸城の天守閣はその後も再建されることはなかった。現在の皇居東御苑の一角に、天守閣の土台である天守台の石垣だけが残っている。
江戸復興にあたり、正之は災害に強い都市に改造する方針を打ち出した。
主要道路の道幅を拡幅し、各地に火除けのための空き地や広小路を作った。
今も地名に残る上野広小路は、この時に作られたものだ。神田川を拡幅し、隅田川には初めて両国橋を架けた。
それまで江戸をはじめ各地の城下町は、戦国時代の発想から、敵から城を守るため道路を狭くして入り組んだ町並みにし、橋は架けないことが常識だった。しかし正之は、戦乱の世はすでに終わったという時代の変化に対応して、町づくりの大転換に踏み切ったのだった。
こうして復興なった江戸の町は本格的な発展を遂げ、わずか30年後には元禄文化の華を咲かせることになる。今日に至る東京の街の基礎は、この時代に作られたと言える。
正之は実は、明暦の大火の6年前にも幕府の別の危機を救っていた。
家康から家光の時代に幕府が数多くの大名を取り潰した結果、大量の浪人が発生し、社会不安が高まっていた。これを背景に家光の死の直後、幕府転覆をめざす由井正雪の乱(慶安の変)が起きたのだ。
事件は未然に防いだが、これを機に、正之の主導で幕府は大名統制政策を転換する。
従来は禁止していた末期養子(藩主の死の直前に跡継ぎを決めること)を認め、大名取り潰しを大幅に減らした。
殉死の禁止にも踏み切った。戦国の気風を残す風習は弊害が多いとして、すでに会津藩では禁止していたが、幕府全体の方針としたものだ。
これら一連の動きは、武断政治から文治政治への転換と呼ばれている。
こうして幕府は、家光の死による政治的動揺と、明暦の大火という危機を乗り切ったのだった。正之の活躍があったからこそ、徳川政権が長期間、持続できたと言っても過言ではない。
ただこれほどの業績を挙げたわりに、保科正之の知名度は一般的に高くない。
明治維新以後、薩長に敗れた会津藩の藩祖である保科正之の影が薄くなったこともあるが、本人が謙虚だったことも原因と考えられる。
正之は「自分はあくまで将軍の後見役。将軍より目立ってはいけない」が信念だったという。死の直前、家臣に命じて自分の業績を記した書類を焼却させたといった話まで残っている。
これには、家光が同母弟の忠長を死に追いやったことが影響しているかもしれない。少しでも野心ありと見なされないよう、細心の注意を払ったとしてもおかしくない。しかしその要素を差し引いても、その謙虚さは並大抵ではない。家光が全幅の信頼を置いたのも頷ける。
こういう点でも、危機に立ち向かうリーダーに求められる条件は何かを、教えてくれているような気がする。
松平定信――天明の大飢饉で 死者ゼロの実績
江戸時代に何度も日本を襲った飢饉の中でも、悲惨だったのが天明の大飢饉(1782〜1787年)だ。
浅間山の大噴火による影響や天候不順、洪水などがたびたび起こり、東北地方を中心に深刻な凶作が続いた。疫病も重なって餓死・病死者は全国で90万人以上にのぼったと伝えられている。
特に南部藩では人口の4分の1に当たる7万5000人、南部藩の支藩である八戸藩では人口の半分の3万人が亡くなったという(諸説あり、正確な人数は不明)。
松平定信が奥州白河藩の藩主となったのは、天明の大飢饉が深刻になり始めていた天明3年(1783)の10月。26歳の時である。
定信は8代将軍・吉宗の次男・田安宗武の七男として生まれたが、17歳の時に白河藩主松平家の養子となっていた。
藩主となった定信はさっそく米の確保に乗り出した。まず越後にあった分領で米1万俵を確保し、急ぎ白河に送らせた。
この米の運搬には会津藩の領内を通過しなければならないため、会津藩の承諾を取り付けたが、その交渉と並行して会津藩からも米を購入する交渉を行い、6000俵を購入することに成功する。
この交渉は定信の藩主就任前の9月に始まっていたが、事実上、定信の指示によるものだったと見ていいだろう。大坂でも別途2000俵の米を買い付けている。
実はこの後になって各藩も米の確保に動き出し、他藩への売り出しを禁ずる措置などをとるのだが、その頃には白河藩はこうして確保を済ませていた。
まさに電光石火の早業である。有事の際には初動がいかに重要かを示している。
しかし当然のことながら、未曾有の飢饉をこれだけで乗り切ることはできない。
江戸にいた定信は、江戸在住の家臣を集めて質素倹約の大号令を発し、自ら衣食を質素にすることを宣言した。領民にも質素倹約を徹底させるとともに、生活が困窮している領民に米を支給するなどの救済策も打ち出している。
豪農や豪商には米や金を拠出させて領民の救済に充て、協力した者には感謝状を板に記した「感札」を与え、それを門に掲げさせたという。
天明3〜4年はいわば飢饉の第一波だったが、白河藩はこれらの対策によって餓死者を出さずに乗り切った。
だが飢饉はなお続く。定信は藩主就任翌年の6月、江戸を発って初めて白河に赴いた。初入部にもかかわらず、その旅は極めて質素な出で立ちだったという。
お国入りした定信が最も重視したのは、やはり質素倹約と農村対策だ。前述の救済策は、今日風に言えば現金給付などの緊急支援策に当たるが、同時に田畑の開墾を進めて食料増産を図った。
宇治から茶の種を取り寄せ栽培させ、田の肥やしになるレンゲソウの栽培を奨励するなど、農業振興にも力を入れた。
来るべき飢饉の第二波、第三波に備えた対策だ。
定信は、役職者の心得を説いた「白河家政録」の中で、「政治の目標の第一は食料の確保にあり、それと倹約により窮民を救済できることや、郡代は農民をわが子のように愛し、農民から親のように慕われるべき」などと述べている(高澤憲治『人物叢書・松平定信』吉川弘文館)。
農業以外でも、幅広く産業振興に取り組んだ。
会津から会津塗の技術者を招いて漆器の生産を奨励したほか、陶器、和紙、ガラスなどの生産も奨励した。
今日になぞらえれば、危機の長期化をにらんだ経済活性化策と言ったところだろうか。
また藩内の意見を吸い上げて政策に生かすことを狙い、城や奉行所の門前、郡代宅などに目安箱を設置した。
尊敬する祖父・吉宗の手法を踏襲したわけだが、併せて白河松平家の祖である松平定綱の霊廟を建設するなどして、藩内の一体感を高める工夫もしている。
飢饉はその後も数年間にわたったが、一連の政策が功を奏し、ついに一人の餓死者も出さなかったと言う。
この成果を引っ提げて、定信は天明7年(1787)、老中首座に就任する。時に30歳。
江戸時代の老中の就任時の平均年齢は45歳(前掲書)であるばかりか、幕府の役職をそれまで全く経験していない身で、しかもいきなり老中の首座である。
現在になぞらえるなら、地方で実績を上げた若い知事が、一足飛びに総理大臣になったようなものだ。
天明の大飢饉では、餓死者を出さなかった東北の藩主がもう一人いた。出羽米沢藩主の上杉鷹山(治憲)である。
この二人には養子という共通点があり、改革を進める際に先祖代々の門閥の重臣たちの抵抗にあっている。
二人ともそれも乗り越えて成果を上げたのだった。
この時代は他にも肥後熊本藩主・細川重賢、出雲松江藩主・松平治郷など、名君と呼ばれた大名が輩出している。
危機に直面した時こそリーダーの実力が試され、優劣の差が出るということだろうか。そんなことを考えていると現在の各知事の姿が思い浮かび、興味深い。
老中首座に就いた定信は、寛政の改革にまい進する。
白河藩で成果を上げた政策を幕府でも実現しようと、飢饉対策の強化、質素倹約、文武奨励などを推進した。農業復興を重視し、帰農令を出して農村人口の回復を図ろうとした。
ただ白河藩で成功した対策が、幕府レベルでもうまくいくとは限らなかった。また前の田沼意次時代の政策を否定し徹底した引き締め政策をとったため、経済の停滞を招き、次第に反発が強まっていった。
「白川の清きに魚の住みかねて もとの濁りの田沼こひしき」
と詠われたのは有名だ。結局、6年後の寛政五年(1793)に、老中を解任されるに至ったのであった。
白河に戻った定信は、その後も藩主として、藩内の飢饉救済や産業振興に力を尽くした。
現在の白河市内に、日本最古の公園と言われる南湖公園がある。
定信が、失業対策事業と経済刺激効果の狙いから享和元年(1801)に築造したもので、完成後は「士民共楽」(武士も庶民も共に楽しむ)の理念の下、憩いの場として親しまれた。広い池とその周りに植えられた桜や楓などの美しい風景が、定信の業績を今に伝えている。
阿部正弘――ペリー来航を機に 新時代への窓を開けた
嘉永6年(1853)6月3日、マシュー・ペリー率いる四隻の軍艦が浦賀沖に現れ、日本は激動の時代が始まった。それは、欧米列強による植民地化の危機との闘いでもあった。
ペリー来航時、幕府は右往左往するばかりで無策だったというイメージが強く、老中首座だった阿部正弘への批判も多い。
しかくよく調べてみると、正弘は無策どころか、当時の常識を超える対策を次々に打ち出して、危機を乗り切ろうとしていたことがわかる。
それらは、後の日本の近代化の先駆けとなる先進的なものばかりだった。
正弘は備後福山10万石の藩主で、天保14年(1843)に25歳の若さで老中に就任、弘化2年(1845)から老中首座となっていた。
阿部家は三河以来の譜代大名で、正弘の父・正精はじめ老中を輩出してきた名門。しかし正弘は単なるお坊ちゃんではなかった。
ペリーが一年後の再来航を予告していったん帰国の途に就いた直後から、正弘は大車輪で動き出す。ペリー退去からわずか3日後の6月15日、江戸湾内防衛のために台場を建設することを、伊豆の代官・江川太郎左衛門英龍に命じたのだ。
江川は10年以上前から、たびたび海防強化についての提言を幕府に提出し、自ら反射炉の模型を作るなどしていた人物で、その手腕を見込んだものだ。
台場は突貫工事で五基を完成させた。そのうちの二基が、現在の東京湾に残るお台場だ。
併せて、大砲製造のため反射炉の建設も江川に命じた。場所は伊豆・韮山。
この反射炉は当時のままほぼ完全な姿で現存しており、平成27年(2015)に、「明治日本の産業革命遺産」の一つとして世界遺産に登録されている。
ただ反射炉が完成したのは安政4年(1857)だった。つまりペリーの再来航には間に合わなかった。
そこで幕府は、すでに独自に反射炉を完成させていた佐賀藩に、大量の大砲製造を急ぎ発注し、その一部を江戸湾まで船で運搬して台場に配備した。
佐賀藩の藩主・鍋島直正は前述の江川英龍と親しく、二人は反射炉や西洋情勢についての情報交換を頻繁に行っていた。
正弘はその鍋島直正とも親しかった。
鍋島家は外様大名だが、そんなことにこだわらず、幅広い人脈を生かして危機乗り切りを図ったのだった。
続いて6月19日には、長崎奉行に対し、オランダから蒸気軍艦を買い入れるよう命じている。
これら一連の動きの大胆な内容とスピード感には、目を見張るものがある。まるで、ペリー来航前から準備していたかのようだ。
正弘の新政策はさらに続く。七月、江戸城に幕閣と外様を含む各大名を集めて、ペリーが持参した米大統領の国書の内容を公開し、意見を求めたのである。
そればかりか、一般の武士や町民などにも意見を募った。幕府始まって以来のことだ。
これも正弘にリーダーシップが欠けていたとよく批判される点だが、むしろ国難を乗り切るためには情報を公開し、知恵を結集することが必要だと判断したからではあるまいか。
それ以前から鍋島直正や薩摩藩主・島津斉彬ら開明的な大名と交流を深め、幕政についての意見も聞いたりしていた。
外様大名に口出しさせるなどご法度だったはずだが、それよりも国難乗り切りを優先させる柔軟な姿勢を持ち合わせていたのだった。
9月には「大船建造の禁」を解禁した。幕府は大名統制策として三代将軍・家光時代の寛永12年(1635)以来、200年以上にわたって大型船の建造を禁止してきたが、正弘は未曾有の危機に対応するため、それを捨てたのである。
これを受け、正弘は幕府自身による軍艦建造の方針を打ち出し、浦賀に造船所を建設させた。同時に、親しかった徳川斉昭率いる水戸藩に命じ、隅田川河口の石川島にも造船所を作らせた。
この両造船所は明治以降、日本の造船業の拠点として発展することになる。
薩摩、長州、佐賀など雄藩は一斉に軍艦建造に乗り出した。
そうして翌年の安政元年(1854)、ペリーが再来航し、日米和親条約が調印された。ついに日本は開国に踏み切ったわけである。まさに幕府の方針の大転換だった。
ペリーの圧力に屈したという側面も否定できないが、これも植民地化を回避しながら新たな事態に対応するという、正弘なりの危機乗り切り策だったと言えよう。
正弘が続いて取り組んだのが海軍創設だった。それまでの幕府には海軍というものがなかった。
前述のとおり、正弘はオランダからの軍艦購入を命じたが、軍艦を使える人材が必要だ。そこで海軍士官を養成する機関、長崎海軍伝習所の創設を決め、安政2年(1855)に開設した。
同伝習所にはオランダの海軍将校を教師として招き、幕臣に操船術や砲術から測量、地理、語学、医学などを学ばせた。その中には勝海舟、榎本武揚らがいた。
注目すべきは、幕府が各藩にも門戸を開いたことだ。それを受けて薩摩や佐賀など有力藩が、数多くの藩士を派遣した。
彼らはここで学んだ成果を自藩に持ち帰って、藩の軍事力と技術力向上に貢献、やがてそれが倒幕につながることとなる。
皮肉なめぐり合わせだが、正弘の努力は幕府や藩の枠を超えて、日本を近代化へと動かしていったことは間違いない。
しかしここで一つ疑問がわく。ペリー来航直後からこれほどの改革を為しえたのなら、なぜもっと早く、ペリーが来る前に動かなかったのだろうか。
ペリーが来ることは、すでにその一年前に、オランダ国王からの親書でわかっていたことだったし、そもそも十年前、やはりオランダ国王が開国を勧める親書を送ってきた時、老中に就任したばかりの正弘は、これを謝絶する返事を出している。
しかしその後の正弘の行動から察するに、機が熟するまで待っていたとも考えられる。
平時での急な改革には抵抗が起きることが予想されるが、トップダウン型のタイプではない正弘としては、外圧をテコに改革を一気に進めることが現実的だったのかもしれない。
正弘がまさにピンチをチャンスに変え、新しい時代への扉を開けたと言えよう。
ただ残念だったのは、安政4年(1857)に39歳の若さで亡くなったことだ。危機との闘いに命を捧げた人生だった
*本稿は、『歴史街道』2020年8月号に掲載した原稿を転載したものです(数字の表記を一部変えています)。