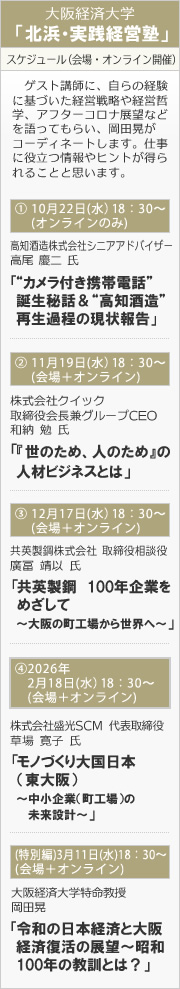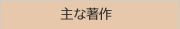Vol. 9 大阪造幣局の「桜の通り抜け」で感じた日本近代化の足跡
(2014年4月22日)
先日、大阪で造幣局の「桜の通り抜け」に行ってきました。毎年ニュースでも報道されるので、ご存じの方も多いと思いますが、遅咲きの桜131品種、350本が560メートルにわたって立ち並び、その光景は美しさを通り越して壮観です。
この桜の木々は造幣局の敷地内に植えられているものですが、満開となる4月中旬の1週間に限って、一般に無料で開放されています。ちょうど敷地内の小道に沿って一方通行で歩きながら桜を見て楽しむことから「桜の通り抜け」と名付けられ、大阪の春に欠かせない風物詩となっています。
その起源は明治16年(1883年)にさかのぼります。造幣局の場所は、もともと江戸時代の大名、藤堂家の屋敷のあったところで数多くの桜が植えられていて、それらを明治になって造幣局が引き継いでいました。当時の造幣局長、遠藤謹助が「局員だけの花見ではもったいない。大阪市民とともに楽しもう」と言って、一般公開が始まったそうです。それ以来、太平洋戦争中と終戦直後の4年間を除いて、毎年開催されています。
この遠藤謹助という人は、知名度はそれほど高くありませんが、「造幣の父」と呼ばれ、日本の近代化に大きな役割を果たした人です。長州藩の出身で、長州藩が幕末の1863年(文久3年)に伊藤博文ら5人の若い藩士を英国に留学派遣した時のメンバーの一人です。この5人は長州5傑、英国では長州ファイブなどと呼ばれました。
実は当時の長州藩は攘夷論を唱え、徳川幕府と真っ向から対立していました。ところがその陰で、こうして藩が5人を英国に留学させていたのです。藩はその費用を負担し、足りない分は借金までして5人を送り出しました。しかも当時の日本はすでに開国していたとはいえ、幕府は一般国民の海外渡航をまだ禁止していましたので、これは密航です。5人のうちの1人、井上聞多(のちの馨、外務大臣)は他家の養子となっていましたが、養子先に類が及ぶのを避けるため、養家から離別して出発したほどです。
そこまでして、なぜ長州藩は彼らを留学させたのか。それは言うまでもなく、海外の情報を直接知るためです。そこに実は明治維新成功の秘密が隠されているのです。
このカギは1864年に起きた下関戦争にありました。下関海峡を通りかかった外国船に対し長州藩が「攘夷を実行」と称して陸地から砲撃をしかけ、欧米4か国の報復攻撃を受けた事件です。ロンドンでこのニュースを知った伊藤博文と井上聞多は急きょ帰国し、停戦と和睦交渉に奔走することになります。
この事件によって、長州藩は欧米との彼我の差を見せつけられ、攘夷論の愚かさを知ったのでした。その結果、外国の優れた技術力と軍事力をむしろ積極的に導入して、藩としての実力を高める方針に転換していったことが、討幕と明治維新につながっていったのです。
攘夷論の急先鋒だったはずの長州が“いつの間にか”攘夷論を捨てて開国論に転換していたわけです。つまり、今日でいうグローバル化の先駆けといえます。
ちょうど同じ時期に薩摩藩も薩英戦争をきっかけに英国との関係改善に動いていました。このように薩摩と長州がともにグローバル化路線に転換したからこそ、薩長同盟が可能となったのです。
遠藤謹助は1866年(慶応2年)まで英国に滞在しましたが、薩摩藩から密航してきた藩士と現地で知り合い交流を深めたと伝えられています。帰国後は、長州藩と英国の協力関係の強化に力を尽くしました。明治維新後は造幣局に入り、造幣局長をつとめました。貨幣の製造は近代国家としての発展上、中核をなすものですから、遠藤の役割の大きさがわかります。
ちなみに、長州ファイブのほかのメンバーは、伊藤博文は周知のように初代総理大臣、井上馨は外務大臣となったほか、山尾庸三は東大工学部の前身となる工学寮を創設して「工学の父」と呼ばれ、井上勝は鉄道庁長官となって新橋―横浜の日本初の鉄道を開業するなど「鉄道の父」と呼ばれました。こうしてみると、遠藤を含む長州ファイブがいかに近代化とグローバル化に貢献したかがわかるでしょう。
今の日本には、こうした幕末から明治にかけての先人たちに学んで、世界に目を向け新しい日本を創るという気概が求められているような気がします。長州といえば安倍首相の出身地でもあります。アベノミクスやTPPが正念場を迎えている今、安倍首相にもそうした突破力を期待したいものです。桜を見ながら、あらためてそんな思いを強くしました。
*本稿は、ストックボイスHPのコラムに掲載した原稿(4月18日付け)を転載したものです。